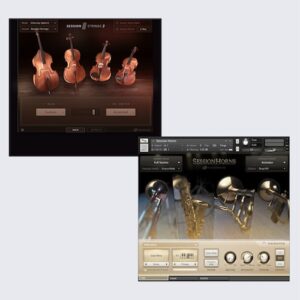アナログのような太いベースを作りたい
デジタル音源では出せない温かみがほしい
そんな想いを持つ人に選ばれているのが、Native InstrumentsのMonarkです。
Monarkは、70年代の名機「Minimoog」を忠実に再現したソフトシンセ。
とはいえ、そのリアルさゆえに「どこから触ればいいのかわからない」と感じる人も少なくありません。
そこでこの記事では、Monarkの構造・音作りの基本・ジャンル別の活用法をわかりやすく解説します。
価格:$99.00
>>>その他Native Instruments製品はコチラ
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。
Monarkとは何か?アナログモノシンセの再現に込められた思想

Monarkは、Native Instrumentsが開発した“アナログモノシンセの再構築”とも言えるソフトウェアです。
1970年代の名機「Minimoog」を細部まで研究し、温かみやわずかな揺らぎまでデジタル上に再現しました。
多くのシンセが「綺麗すぎる」音を出す中で、Monarkはあえて“完璧でない”サウンドを再現し、音楽に有機的な生命力を与えています。
3基のオシレーター:
各オシレーターが異なる波形特性を持ち、音を重ねると微妙な位相のずれによる厚みが生まれます。
デチューンを加えることで、ビンテージ特有の太さを再現可能です。
4ポール・ラダーフィルター:
Minimoog直系のフィルター構造を再現。
カットオフを下げると音が丸くなり、レゾナンスを上げると自己発振し、滑らかにうねるアナログ感が得られます。
ドリフトとリークのモデリング:
電圧や温度変化によるピッチの揺れや、わずかに音が漏れる現象を再現。
これにより、完全にデジタルではない“息づく音”が得られます。
高サンプルレート設計:
88.2/96kHzの処理を前提に設計されており、倍音の滑らかさと高域の自然な空気感を実現します。
演奏感を重視したUI:
Reaktor上で動作し、ノブ操作の反応速度やカーブが実機の感触に近づけられています。
マウス操作でも生演奏のようなリアルなフィードバックを得られます。
MonarkはMinimoogの何を再現しているのか

Monarkの最大の特徴は、Minimoogの構造をソフトウェア上で忠実に再現している点にあります。
3基のオシレーター、独特なミキサー構造、4段階のラダーフィルター、そして滑らかなグライド。
どの要素も音楽史に残るサウンドを生み出した重要な構成要素です。
オシレーターの倍音設計:
それぞれの波形にわずかな非対称性があり、単音でも独特の厚みが出ます。
三角波や鋸波を重ねると倍音の干渉で豊かな響きになります。
ピッチの揺らぎ(チューニングの不安定さ):
わざと僅かなズレを導入し、長時間の演奏でも“生きている音”を再現します。
一定ではない揺れが音に深みを加えます。
アナログサチュレーション感:
増幅段の歪みを忠実に再現し、音を飽和させることで存在感を出します。
中低域の厚みが増し、リードでも前に出る音になります。
レゾナンスの挙動:
高音域で急激に立ち上がる独特のピーク感を再現。
少し過剰な設定にすることで実機同様の“鳴き”が得られます。
フィードバック回路の歪み:
A/Bの2モードを搭載し、温かい倍音から過激なディストーションまで再現可能。
ハード機材のようなエネルギー感を生み出します。
アナログらしさを再現するための設計思想
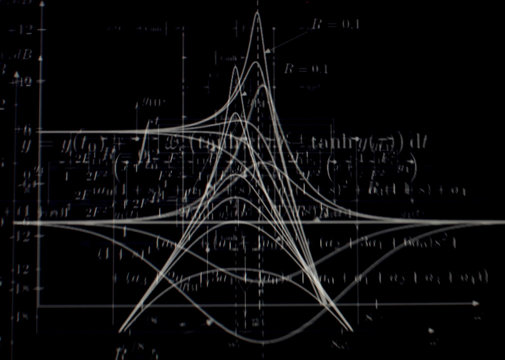
Monarkが他のシンセと一線を画すのは、「完璧ではない音こそが心地よい」という設計思想です。
わずかな音の揺らぎ(ドリフト)や、音が完全に消えず残るリークノイズなど、人間味のある不安定さをあえて再現しています。
オシレーターごとの微小ドリフト:
同じ波形でも少しずつ音程が揺らぐように設計されています。
結果として、厚みと温かさが自然に生まれます。
フィルター段のノイズリーク:
信号を完全に遮断せず、わずかに通すことで実機の“空気の振動”を再現しています。
静寂の中にも息づく感覚を残します。
温度変化による挙動のモデリング:
時間とともに音程がゆっくりズレるような動作を再現。
長いサステインでも平坦にならず、微妙な緊張感を保ちます。
残響する空気感の再現:
音を完全にゼロにせず、ミックス内で自然に馴染むように設計。
トラック全体の“深さ”を感じさせます。
View Bによる微調整機能:
リーク量やドリフト強度を自由に変更可能。
自分の理想に合わせて“ビンテージ度合い”を調整できます。
Native Instruments「Monark」の価格

価格:$99.00
>>>その他Native Instruments製品はコチラ
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。
Monarkの特徴と音質が「本物」と言われる理由
Monarkが“本物のアナログ感”と評価される理由は、単に音が似ているからではありません。
音の生成から変化までの一つひとつの挙動を、アナログ回路そのものの動作として再現している点にあります。
デジタルでは通常カットされる微細なノイズや倍音の重なりを残し、結果として有機的で奥行きのあるサウンドを生み出します。
リアルな倍音構成:
波形ごとの倍音を独立モデリングし、オシレーター同士を重ねた際の“濁り”や“ぶつかり”まで再現しています。
演奏するたびにわずかに異なる響きを感じます。
非線形フィルター処理:
4ポールラダー型のフィルター回路を再現し、入力信号に応じて反応が変化。
カットオフの動きに温度を感じる滑らかさがあります。
エンベロープのアナログ特性:
ADSRではなくADSタイプを採用。音の立ち上がりや減衰の挙動を滑らかに保ち、連続した演奏でも自然な流れになります。
信号経路のドライブ特性:
MIXER段やフィルター前段で生じる微小な歪みを再現。
音量を上げるほど倍音が増し、サチュレーションが心地よくかかります。
モジュレーションの相互干渉:
オシレーター3をLFOとして使用することで、ピッチとフィルターが同時に揺れるような複雑な変化を生みます。
静止した音がほとんど存在しません。
3基のオシレーターが生み出すアナログ的な厚み
Monarkのサウンドの基礎を作るのが3基のオシレーターです。
それぞれに個別の波形、レンジ、周波数を設定でき、音の重なり方が極めて自然です。
単体でも十分に存在感がありますが、3基を組み合わせることで倍音が複雑に干渉し、独特の“アナログのうねり”が生まれます。
オシレーター1(基準波):
常に安定したチューニングを保ち、他のオシレーターの基準音として働きます。
これにより音全体の重心がぶれません。
オシレーター2(デチューン用):
わずかにピッチをずらすことで、ビートのような揺れを作り出します。
ベースでは太さを、リードでは立体感を強調します。
オシレーター3(モジュレーション兼用):
LFOとしても利用可能で、ピッチやフィルターを周期的に揺らします。
静止しない音の変化が、アナログらしい生命感を加えます。
波形選択の組み合わせ:
鋸波+矩形波など、異なる波形を重ねることで倍音バランスが変化します。
柔らかさから荒々しさまで自在に調整可能です。
低域の安定感:
オシレーターの基音が重なるとローエンドに厚みが出ます。
ベースラインに深みと存在感が生まれ、ミックス全体を支えます。
フィルターとレゾナンスの構造:滑らかさと自己発振の再現
Monarkに搭載されたフィルターは、名高いラダー型フィルターをモデルにしています。
24dB/Octの急峻なカット特性を持ちながら、入力信号に応じて自然に飽和する柔軟な挙動が特徴です。
音量や倍音によって反応が変化し、操作するたびに生きた感触を得られます。
MMモード(24dB/Oct):
クラシックなローパス特性で、濃密な低域と丸みのある中域を再現します。
ベース音作りに最適です。
LP2・LP1モード:
フィルターのカーブを浅くし、音の抜けを向上。
リードやパッドで明るい印象を出したいときに有効です。
BPモード(バンドパス):
中域を際立たせ、エレクトロやFX的なサウンドに変化させます。
ノイズを混ぜると“声”のような質感が得られます。
レゾナンス設定:
強めると自己発振し、ピッチをもつようになります。
キートラッキングを併用すれば、フィルター自体をメロディ的に演奏することも可能です。
入力レベルとの相互作用:
MIXER段の“LOAD”ノブで信号を増幅すると、フィルターが自然にドライブ。
温かみと歪みを両立できます。
「ドリフト」と「リーク」が生み出す温かみ
Monarkのリアルさを支えているのが、アナログ機材特有の“癖”を再現するドリフトとリークです。
どちらも一見ノイズのように思えますが、これらがあることで音に奥行きと自然なゆらぎが加わります。
ドリフト(Pitch Drift):
電圧の不安定さによる微小なピッチ変動を再現。
長い音でも一定にならず、耳に馴染む自然な揺れを生みます。
リーク(Leakage):
オシレーターの出力が完全に遮断されず、小さく残る現象です。
音が完全に途切れず、空気のような残響が漂います。
温度変化モデル:
時間の経過とともに微妙に音が変化するよう設計。
特に持続音では、音が“呼吸する”ような印象を与えます。
View Bでの微調整:
ドリフト量やリーク量を調整することで、現代的なクリーンさからヴィンテージ感の強いサウンドまで自在に変化させられます。
ミックス全体への効果:
揺らぎのある音は他トラックと馴染みやすく、空間的な広がりを生みます。
結果としてデジタル臭さが消え、自然な一体感が得られます。
Monarkの使い方:基本操作と設定ポイント
MonarkはNative InstrumentsのReaktorプラットフォーム上で動作します。
インターフェイスはシンプルですが、実際に触ると奥深く、各ノブの動きが音に直結する構造です。
まずは、立ち上げ方から各パネルの違い、そして音色の保存方法まで、制作をスムーズに進めるための基本操作を押さえましょう。
起動環境:
ReaktorまたはReaktor Playerで動作します。
インストール後、スタンドアロン起動かDAWのプラグインとして使用可能です。
インターフェイス構成:
メインとなる「パネルA」と、詳細設定が可能な「パネルB」に分かれています。
基本操作はすべてパネルAで完結します。
操作レスポンス:
ノブを回したときの追従性やカーブはアナログ実機に近く、わずかな操作でも音が大きく変化します。
細かい調整が重要です。
スナップショット管理:
気に入った音はスナップショットとして保存可能。
ジャンル別フォルダを作ると制作効率が上がります。
MIDIマッピング:
外部MIDIコントローラーを割り当ててリアルタイム演奏が可能。
ライブセットでも即戦力になります。
ReaktorでMonarkを起動する手順
Monarkを使うには、まずReaktorまたは無料のReaktor Playerを立ち上げる必要があります。
操作はシンプルで、一度覚えれば次回からすぐに作業を始められます。
Reaktorを起動:
Native AccessからReaktorをインストールし、スタンドアロンまたはDAW上で開きます。
どちらの方法でもMonarkは同様に動作します。
Monarkを読み込む:
メニューの“Player”もしくは“Ensemble”からMonarkを選択。
数秒でロードが完了し、パネルAが表示されます。
音が出ないときの確認:
Reaktorの“Audio”設定で出力デバイスを確認。
MIDI入力先も正しく設定されているかチェックします。
初回起動後の保存:
自分の環境に合わせたパラメーターやオーディオ設定を“Snapshot”として保存すると、次回以降の立ち上げがスムーズです。
DAWでの使用:
VST/AUプラグインとしてDAW上に読み込むことで、他のトラックとミックスしながら音作りが可能になります。
パネルA・Bの違いと使い分け
Monarkの操作画面は「パネルA」と「パネルB」の2つに分かれています。
見た目はシンプルですが、音の仕組みを理解すると、両者を切り替えて使うことで音作りの幅が大きく広がります。
パネルA(表側):
オシレーター、ミキサー、フィルター、エンベロープなど、実際に音を作る主要操作を集約。
演奏時のリアルタイム操作に最適です。
パネルB(裏側):
ドリフト量、リークノイズ、キートラッキング、ピッチベンドレンジなど、細かな挙動を設定できます。
音の質感を追い込みたいときに使います。
音の再現度:
パネルBで微調整することで、より実機に近い挙動を得られます。
特にドリフト値の調整は音の生々しさに直結します。
表示切り替え:
右上の「View」ボタンでワンクリックで行えます。
編集作業と演奏操作をスムーズに行き来できます。
初心者のポイント:
最初はパネルAだけでも十分です。
慣れてきたらパネルBで“味付け”をするイメージで扱うと自然に理解が深まります。
スナップショットで音色を管理する方法
Monarkには“Snapshot(スナップショット)”と呼ばれるプリセット管理機能があります。
音色を保存・呼び出しできるだけでなく、制作中の比較検討にも役立ちます。
スナップショットの保存:
音が決まったら、上部メニューのカメラアイコンをクリックして保存。
名前を付けることで後から探しやすくなります。
フォルダ管理:
ジャンルごとにフォルダを分けて保存すると便利です。
たとえば「Bass」「Lead」「Pad」など用途別に整理しておくと作業効率が上がります。
呼び出しの手順:
スナップショット一覧から選ぶだけで即座に音色を切り替え可能。
ライブパフォーマンスでも瞬時に切り替えられます。
比較活用:
音作り中に複数の設定を保存しておけば、A/B比較が簡単に行えます。
微妙な音の違いを判断するのに役立ちます。
バックアップの推奨:
Reaktorのフォルダごと定期的にバックアップしておくと、PCトラブル時にも安心です。
特にオリジナルパッチを多用する人は必須です。
Monarkの音作り入門:ベースとリードを自在に操る
Monarkの真価は、ベースとリードの音作りにあります。
シンプルな構成ながら、わずかなノブの調整で音のキャラクターが劇的に変わるのが特徴です。
まずは基本的な考え方を押さえ、定番のベースとリードサウンドを組み立てる手順を理解しましょう。
音作りの基本構造:
音の土台を作るのは3基のオシレーターです。
波形の組み合わせとピッチ設定で音の性格が決まります。
ミキサー段の役割:
各オシレーターの音量を調整してバランスをとります。
強くしすぎるとフィルターがドライブし、歪みが加わります。
フィルターとエンベロープ:
音の明暗と時間的な動きを作る要素です。
ベースでは短く鋭く、リードでは緩やかに設定します。
フィードバックの重要性:
出力を入力に戻すことで、音に倍音と圧力を加えます。
軽くかけるだけで存在感が一段上がります。
最後に調整するポイント:
グライドやモジュレーションで音に流れや表情を加えると、単なるシンセ音から“演奏感のある音”へと変化します。
ベース音を太くするための設定とテクニック
Monarkのベースは、太く・抜けがよく・温かいのが特徴です。
低域を支えるだけでなく、トラック全体の厚みを作る中心的な役割を担います。
ここでは、安定した低音を出すための実践的な設定を紹介します。
オシレーター設定:
オシレーター1を基音、オシレーター2をやや下にデチューン。
矩形波または鋸波を使用し、音に厚みを加えます。
フィルター設定:
カットオフを200Hz前後に設定し、レゾナンスを控えめに。エンベロープで軽く開くように設定すると、アタックが強調されます。
エンベロープ調整:
アタックを速く、ディケイを短め、サステインは中程度。
これにより、キックと干渉せずタイトなベースになります。
フィードバックの活用:
フィードバックAを少し上げると中低域に圧力が加わり、音が前に出ます。
やりすぎると歪むため注意が必要です。
EQ・ミックス処理:
40〜60Hzを軽くブーストし、300Hz付近を少しカット。
これによりベースの芯を残しつつ、ミックスの抜けが良くなります。
リード音に抜けと存在感を出すコツ
リードサウンドは曲の主役となるため、抜けの良さと音の艶が重要です。
Monarkでは、オシレーターの組み合わせとフィルター設定の工夫でプロ品質のリードを作ることができます。
波形の選択:
鋸波をメインに、矩形波を軽くブレンド。倍音が豊富になり、サウンドが前に出ます。
ピッチ設定:
オシレーター2をわずかに上にデチューンして厚みを出します。
過剰にずらすと音が濁るので±5cent程度が目安です。
フィルター調整:
カットオフを開き気味にして、明るく抜ける音を作ります。
レゾナンスを少し上げると音が前方に立ち上がります。
エンベロープの設定:
アタックを少し遅めに、ディケイを中程度に設定。
滑らかな立ち上がりと柔らかな余韻が得られます。
モジュレーションの追加:
オシレーター3をLFOモードにしてピッチを微妙に揺らすと、アナログ特有の“歌うような”リードになります。
フィードバックA/Bを使い分けて歪みをコントロール
Monarkには「フィードバックA」と「フィードバックB」という2種類のフィードバック経路があります。
両者を理解して使い分けることで、音のキャラクターを自在に操ることができます。
フィードバックA:
出力を入力前段に戻す伝統的な方式。中低域が厚くなり、サチュレーションが自然に加わります。
ベースに最適です。
フィードバックB:
より後段に信号を戻す設計で、音が鋭くアグレッシブになります。
リードやエフェクト的なサウンドに向いています。
適用バランス:
Aを中心に少しBを混ぜると、温かさと抜けの両立が可能です。
Bを強めると歪みが増え、ローファイな印象になります。
過度な設定の注意点:
フィードバックを上げすぎると全体のゲインが上がり、音割れや耳障りなノイズが発生します。
小さな変化を確認しながら調整しましょう。
実用的な組み合わせ:
ベースではAを中程度、Bをゼロに。
リードではAを控えめにしてBを25〜30%に設定すると心地よい歪みが得られます。
Monarkの上級テクニック:アナログ感を極める調整術
Monarkには、表からは見えない「裏設定」が数多く存在します。
これらを調整することで、音のリアルさや揺らぎ、演奏感をさらに深めることができます。
特に“View B”に切り替えて操作するパラメーターは、アナログ実機を超える柔軟性を備えています。
音の安定度を下げることで、わずかに不安定な“生きた音”を得ることができるのです。
View Bの役割:
通常は隠れている詳細設定を表示します。
音の癖や反応を微調整でき、モデリングシンセらしさを存分に発揮できます。
微細なパラメーター群:
ドリフト、リーク、ピッチ安定度、ノイズ成分など、アナログ機材の“個体差”を再現する要素が集約されています。
クリエイティブな応用:
音の温度感を調整したり、ドリフトを強めてローファイな雰囲気を演出するなど、ジャンルに応じた表現が可能です。
再現性とリアリティの両立:
View Bを使えば、アナログの不安定さを保ちながらも、保存と再現が可能。
制作と演奏の両面で安心して使えます。
実践のコツ:
1つのパラメーターを大きく動かすのではなく、少しずつ複数を組み合わせて調整するのが自然な仕上がりのコツです。
Oscillator DriftとLeakageの微調整
ドリフトとリークは、Monarkの“生命感”を作る最重要要素です。
デジタルでは排除されがちなわずかなズレや漏れを加えることで、音に温度が宿ります。
View Bでの設定は数値が細かく、少しの調整でも印象が大きく変化します。
Oscillator Drift(ドリフト):
ピッチがゆっくり揺れるように変化します。
値を上げると音が不安定になり、古い機材特有の味が出ます。低く設定すると現代的でタイトな音になります。
Drift Rate(揺れの速度):
ゆっくりした設定は深みを生み、速い設定は不安定な個体のようなキャラクターになります。
曲調に合わせて変化させましょう。
Leakage(リーク):
完全に遮断されない微量の信号がフィルター段に残るようになります。
音が完全に消えず、自然な残響が生まれます。
Leakage Type:
ランダム性を変化させ、どの周波数帯でリークが発生するかをコントロールします。
ベースでは控えめ、リードではやや多めが効果的です。
実用的な調整例:
ドリフト20〜30%、リーク10〜15%程度で、安定しすぎず不安定すぎない自然な質感が得られます。
キートラッキングとチューニングで表現をコントロール
アナログシンセの魅力は、鍵盤の位置によって音の響きが変化することです。
Monarkではキートラッキングを調整することで、高音域では明るく、低音域では厚みを増すような自然な変化を作り出せます。
Key Tracking(キートラッキング):
カットオフ周波数が鍵盤の高さに応じて変化します。
100%ではピッチに正確に追従し、値を下げると高音がやや暗くなります。
チューニング微調整:
各オシレーターにわずかなズレを加えることで、アナログ特有の揺らぎを演出します。
完全な同調ではなく、±3cent程度の差が自然です。
ハイエンドの扱い:
高音域でのトラッキングを軽く抑えると、刺さりすぎず耳馴染みの良い音になります。
ベースでの設定例:
Key Trackingを70〜80%に設定。
低音が太く、高音がやや落ち着いたトーンになります。
リードでの設定例:
Key Trackingを100%にし、オシレーター3を微妙に揺らすと、音が上に抜けるような爽快感が生まれます。
Mod WheelとPitch Bendの活用で表情をつける
Monarkは演奏中の表現力を高めるために、モジュレーションホイールやピッチベンドの反応を細かく設定できます。
シンプルな操作でも、音が息をするように変化し、ライブ演奏に強い存在感を与えます。
Mod Wheel(モジュレーションホイール):
LFOの深さをリアルタイムで調整します。
揺れを加えることで、メロディに動きと感情が生まれます。
Pitch Bend Range:
音を上下に滑らせる幅を設定できます。
±2〜5セント程度なら自然で、±12セント以上にすると大胆なグリッサンド表現が可能です。
ベロシティとの連動:
鍵盤の押し込み強度に応じて、フィルター開閉や音量変化を連動させることができます。
演奏に立体感を加える方法です。
実践的な設定例:
リードでは、Mod Wheelでビブラート、Pitch Bendでスライドをコントロール。
ベースでは、ピッチベンドを控えめにして安定感を優先。
演奏時のポイント:
常に強く動かす必要はありません。
フレーズの区切りや終わりにさりげなく使うと、音楽に呼吸を感じさせられます。
Monarkをジャンル別に活用する:実践的サウンドデザイン
Monarkは、アナログモノシンセとしての汎用性が非常に高く、ジャンルを問わず存在感を発揮します。
音の太さ・反応の速さ・温かみのある倍音構成により、エレクトロ、ヒップホップ、ロックなど幅広いシーンで使われています。
ここでは、各ジャンルに合わせた設定の方向性を解説します。
ジャンル別の特性理解:
音楽のジャンルによって、求められるアタック感・倍音量・リズムの密度が異なります。
Monarkではそれを直感的に調整できます。
リズムとグルーヴの関係:
オシレーターの揺れやフィルターのカーブが、リズムの「ノリ」に大きく関わります。
テンポ感に合わせた設定が重要です。
トラック全体での役割:
ジャンルごとにMonarkを「ベース主体」「リード主体」「効果音的」として使い分けると、トラックに統一感が生まれます。
モジュレーションの使い方:
過度な動きを避け、低域を安定させつつ中高域で変化を出すと、どのジャンルでも使いやすくなります。
ジャンル横断的な魅力:
どんな音楽でも「Monarkらしい深み」を保てるのは、アナログ特有の倍音の揺らぎと自然な空気感があるからです。
ヒップホップ向け:ローエンドを支えるグルーヴベース
ヒップホップでは、トラックの重心を支える“太く粘りのあるローエンド”が重要です。
Monarkのベースサウンドは、まさにこの要素を自然に実現できます。
波形の選択:
矩形波をメインに、わずかに鋸波を混ぜて倍音を加えます。
これにより低音がしっかり出ながら、トラック内で埋もれません。
フィルター設定:
カットオフを150Hz付近に設定し、レゾナンスを弱めに。
アタックを抑えることで、キックとの干渉を避けます。
ドリフト調整:
わずかにドリフトを加えると、リズムに“人間的なズレ”が生まれ、ループにグルーヴ感が出ます。
エンベロープ設計:
ディケイを短く設定し、アタックを強めに。
低音を支えつつ、リズムの粒が感じられる音になります。
ミックス処理:
40Hz以下を軽くローカットし、100Hz前後をブースト。
結果としてキックとのバランスが取りやすくなります。
エレクトロ/テクノ向け:モジュレーションで動きを出す
エレクトロやテクノでは、単調な音の繰り返しではなく、時間的な変化が曲全体のドライブ感を作ります。
Monarkはこの「動きのある音作り」に非常に強く、少ない操作で躍動的なグルーヴを作り出せます。
LFOの活用:
オシレーター3をLFOモードに設定し、フィルターカットをゆっくり揺らします。
これによりリズムの波を感じるサウンドになります。
レゾナンスの自動変化:
モジュレーションホイールを使ってレゾナンスをリアルタイムにコントロールすると、音の緊張感が生まれます。
ステップ的なカット変化:
DAWのオートメーションを使ってフィルターを細かく変化させると、電子的でトリッキーな印象になります。
エンベロープの動き:
短いディケイと高めのレゾナンスを組み合わせると、スネアのようなパーカッシブな質感を作れます。
モジュレーション深度:
あえて過剰に設定して“暴れる音”を作ると、クラブトラックで存在感を放つ独特なサウンドになります。
ロック/インディー向け:リードで抜けるアナログサウンド
ロックやインディー系では、ギターやボーカルと並んでも存在感を失わない“太く抜けるリード”が求められます。
Monarkのリードサウンドは、アナログ感とモダンさを両立し、バンドサウンドにも自然に溶け込みます。
波形の組み合わせ:
鋸波を基本に、矩形波を少し加えることで中域が強調されます。
ギターと干渉しにくく、音が前に出やすくなります。
フィルターの開き方:
カットオフを開き気味に設定し、軽くレゾナンスを加えます。
リード音に明るさと輪郭が生まれます。
エンベロープの調整:
アタックをわずかに遅らせると、ボーカルや他の楽器と馴染みやすくなります。
サステインを中程度にして持続感を確保します。
フィードバックの使用:
Bモードを25〜30%に設定。軽い歪みを加えることで、ギターアンプのような“荒さ”を持たせます。
空間系エフェクト:
外部で軽くディレイやリバーブをかけると、音が広がり、ライブ感のある存在感が得られます。
他シンセとの比較で見るMonarkの個性
Monarkは数あるMinimoog系エミュレーションの中でも、最も実機に近い質感を持つと評されます。
その理由は、単に音が似ているだけでなく、波形生成から信号経路、フィードバック挙動まで“回路の癖”を忠実に再現している点にあります。
他のソフトシンセと比べることで、Monarkの独自性がより明確になります。
再現精度の高さ:
電子回路レベルでのモデリングにより、倍音の密度と温かみが実機に極めて近いです。
音の反応速度:
ノブを操作したときの反応がアナログ特有の滑らかさを持ち、動作が自然です。
CPU負荷と効率性:
高解像度処理ゆえにCPU負荷はやや高めですが、その分音の密度感が格別です。
他製品との比較観点:
Arturia、UAD、Moog Model Dなど、同系統シンセとの違いを理解することで、Monarkの音作りの方向性が見えてきます。
選ばれる理由:
多くのプロデューサーが「トラックに置いた瞬間に音が決まる」と評価する、その即戦力がMonarkの最大の強みです。
各ソフトシンセとの音質比較表
Monarkは、同じMinimoog系のソフトシンセと比べても独自のキャラクターを持っています。
以下の比較では、音質傾向や操作性の違いを明確に整理しています。
| シンセ名 | 音の傾向 | 特徴 | 操作性 | 適した用途 |
|---|---|---|---|---|
| Monark(Native Instruments) | 厚みがあり温かい | 回路モデリングが正確、倍音が豊か | 直感的、視認性が高い | ベース、リード、クラシックシンセ再現 |
| Mini V(Arturia) | やや明るく現代的 | EQとエフェクトが豊富 | 柔軟で拡張性が高い | EDM、ポップ、シンセポップ |
| Moog Model D(UAD) | 実機的で滑らか | ダイナミクスが広くアナログ感が強い | やや重いが精密 | 実機代替、リッチなベースサウンド |
| Legend(Synapse Audio) | 非常に精密でクリーン | アナログ特有の揺らぎも再現 | 軽量で安定 | モダンシンセ、DAW制作全般 |
| MiniMonsta(GForce Software) | 厚みと派手さを両立 | 追加LFOやモジュレーション豊富 | やや複雑 | 実験的音作り、サウンドデザイン向け |
比較のポイント:
Monarkは“実機の存在感”に最も近く、他製品が持つ拡張機能や軽さよりも「質感の再現」を重視しています。特に低域の安定感と中域の太さは、他のどのソフトシンセにもない強みです。
プロがMonarkを選ぶ理由
Monarkがプロフェッショナルに選ばれるのは、「録音した瞬間に完成形の音が出る」からです。
余計なエフェクト処理をしなくても、ミックスの中で自然に馴染む音を持っています。
これは、倍音構造と信号の反応特性がリアルに再現されているためです。
ミックスでの扱いやすさ:
他のシンセのようにEQで整えなくても、すでにバランスが取れた音が出ます。
結果として制作スピードが格段に上がります。
ジャンル対応力:
ヒップホップの太いベースから、エレクトロの鋭いリード、ロックの温かいリードまで一台でカバー可能です。
音の存在感:
音の芯が太く、他のトラックと混ざっても埋もれにくい。
ローからハイまで自然に広がるのが特徴です。
ノブ操作のリアリティ:
操作感が直感的で、わずかな調整でも実機のような手応えがあります。
作り込みよりも“演奏で音を作る”感覚に近いです。
制作現場での信頼性:
長年アップデートが続いており、安定性も高く、どのDAWでも問題なく動作します。
即戦力として導入される理由です。
Monarkを最大限に活かす設定と実践Tips
Monarkは高精度なアナログモデリングのため、環境設定や使い方次第で音の印象が大きく変わります。
特にサンプルレートやCPU負荷の管理は、音質とパフォーマンスを両立するうえで重要です。
ここでは、制作やライブ環境でMonarkを安定的に運用するための実践的なポイントを紹介します。
音質を引き出す環境設定:
高いサンプルレートほど滑らかで自然な倍音が得られます。
制作環境に合わせて最適なバランスを見つけましょう。
CPU負荷対策:
モデリング精度が高いためCPU消費が多いですが、工夫次第で軽く動かせます。
プロジェクト管理の重要性:
パッチやスナップショットを整理し、バージョン管理を行うことで再現性を高められます。
DAWとの連携:
各DAWのオーディオ設定を理解し、遅延補正やバッファサイズを適切に設定することで動作が安定します。
制作効率化の考え方:
テンプレート化しておくと、毎回の設定を短縮でき、制作に集中できます。
推奨サンプルレートとオーディオ設定
Monarkは高解像度のモデリングを行うため、サンプルレート設定が音の品質に直接影響します。
適切なレートを選ぶことで、音の滑らかさとCPU負荷のバランスを取ることができます。
標準サンプルレート(44.1kHz/48kHz):
一般的な制作環境向け。CPU負荷が低く、ベースやリードの音も十分に自然に鳴ります。
ポップスやロックなど幅広いジャンルに適しています。
高サンプルレート(88.2kHz/96kHz):
倍音の滑らかさが格段に向上し、フィルターの動きもより自然になります。
高音域が透き通り、プロダクション用途に最適です。
CPU負荷とのバランス:
高サンプルレートではCPU使用率が上がるため、必要に応じてDAW側のバッファサイズを増やして安定化させます。
モニタリング環境:
解像度の高いオーディオインターフェースとヘッドフォンを使用することで、音の違いを正確に判断できます。
最適な設定例:
制作時は88.2kHzで録音し、ミックス段階で44.1kHzに変換するのが、音質と効率のバランスが良い方法です。
CPU負荷を抑えつつ音質を保つ方法
Monarkはリアルなアナログ挙動を再現するため、他のソフトシンセよりもCPU負荷が高くなりがちです。
しかし、いくつかの工夫で高音質を維持しながら軽快に動かすことが可能です。
不要な機能をオフにする:
使用していないオシレーターやドリフト設定をオフにすると、処理が軽くなります。
特に3基すべてを使わない場合は1つ停止するだけでも効果的です。
エフェクトを後段で処理:
リバーブやディレイなどはDAWのプラグインで後がけにすると、Monark自体の負荷を抑えられます。
レコーディング時のバウンス:
トラックごとにオーディオとして書き出し、再生時のCPU負荷を軽減します。
複数インスタンスを同時に使用する際に有効です。
ドリフトとリークの調整:
これらの値を控えめにすることでCPU使用率が安定し、動作が軽くなります。
音の雰囲気はそのまま保たれます。
DAW側のバッファ設定:
バッファサイズを512〜1024に上げると処理落ちを防げます。
録音時は低く、ミックス時は高めに設定するのがコツです。
プロジェクト保存・再現性を高める工夫
Monarkは設定項目が多く、音作りに没頭していると再現が難しくなることがあります。
プロジェクトを安定して再現できるように、整理と記録の仕組みを整えておくことが重要です。
スナップショットの活用:
完成した音色は必ずスナップショットに保存しておきましょう。
プロジェクトを再度開いたときに音が変わるのを防ぎます。
命名規則の統一:
プリセット名に「曲名+用途(例:Bass_DeepGroove)」のような形式を使うと、後で探しやすくなります。
プロジェクトごとのフォルダ管理:
各楽曲のプロジェクトフォルダ内に“Monark Presets”を作っておくと整理が簡単です。
バージョン管理:
音作りを進めるたびに「ver1」「ver2」と保存。
戻したい時に比較しやすく、制作の過程を追いやすくなります。
バックアップとクラウド保存:
Native Accessのライブラリと合わせて定期的にバックアップすることで、システム移行やトラブルにも対応できます。
動作環境(System Requirements)
Monarkは Reaktor エンジン 上で動作します。
使用には Reaktor または Reaktor Player(最新バージョン) が必要です。
Monarkまとめ:Native Instruments「Monark」40年の人気音楽の中心にあったシンセサイザーの全ニュアンスを驚異的ディテールでキャプチャ!エレクトロニック・ヒップホップ・インディー・ロック全ジャンルでベース・リード音の第一選択肢として君臨し続けるアナログ・モノシンセの王者|DTMプラグインセール
Monarkは、単なるヴィンテージ・シンセの模倣ではありません。
1970年代の名機「Minimoog」が持っていた“音の生命力”を現代の制作環境で蘇らせた存在です。
太く温かい低音、表情豊かなリード、そして実機さながらの揺らぎ──
これらが融合することで、Monarkは今なお多くの音楽家に選ばれています。
- 実機に迫るアナログの質感と倍音構造
- 直感的に操作できる設計と安定した挙動
- ジャンルを問わない高い汎用性
- 制作現場で即戦力となる音の完成度
- 継続的なサポートとReaktor環境での互換性
その結果、Monarkは“クラシックを現代に再構築したシンセ”として、過去と未来をつなぐ架け橋のような存在になっています。
音作りを始めたばかりの人から、長年のプロデューサーまで──
誰が触っても「音楽的な結果」が得られる、それがMonarkの本当の魅力です。
価格:$99.00
>>>その他Native Instruments製品はコチラ
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。