
音を「動かす」ことで空間を演出する、そんな新しい音響体験が注目を集めています。
視覚的に動きを確認できる3Dビューポートや、バイノーラル対応の空間処理により、従来の空間系VSTとは一線を画します。
この記事では、Frahmの基本機能から使い方、他プラグインとの違い、そして初心者でも扱いやすいポイントまで、分かりやすく解説していきます。
価格:$55.00
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。
Frahmとは何か?革新的な空間オーディオの基礎を解説
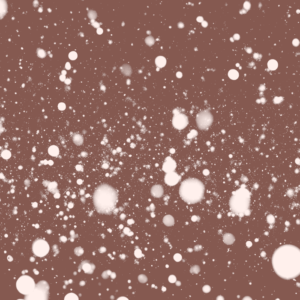
Frahmは、Leseが提供するユニークな空間音響プラグインで、音を「移動させる」ことを中心に設計されています。
特徴的なのは、仮想空間内でパーティクル(粒子)を動かし、それぞれを音源として扱うという点です。
この手法により、聴き手のまわりを音が回るような立体的なサウンドを生み出せます。
その結果として、従来のパンニングやディレイだけでは表現できなかった動きのある音響演出が可能になり、楽曲制作はもちろん、映像やインスタレーション、VR作品においても強力な表現ツールとなります。
- パーティクルシステム:
無数の仮想粒子が空間内を移動し、それぞれが音源として働く設計 - ベクターフィールドアルゴリズム:
音の動きを制御する10種の力場を用意。物理的な挙動に基づいて変化する - リアルタイムレンダリング:
OpenGLによるビジュアル表示で動きを確認しながら操作ができる - クロスフェード制御:
異なる2つの力場を滑らかに切り替えて音の動きに変化をつけられる - 複数インスタンス対応:
DAW内で複数のFrahmを重ねて使用し、複雑な空間音響を構築可能 - バイノーラル/ステレオ対応:
ヘッドホンとスピーカーのどちらにも最適化された出力方式を選択できる
Frahmはどんなプラグイン?基本機能と開発背景

Frahmは、「音の動き」をテーマに設計されたジェスチャル・プロセッサー型のオーディオプラグインです。
開発元のLeseは、物理演算やビジュアル制御に強みを持つ開発集団であり、従来のミキシング手法とはまったく異なるアプローチで空間音響の可能性を広げています。
このプラグインは、単なるエフェクトではなく、「動く音を作るためのシミュレーター」に近い存在です。
このことから、サウンドデザインやライブパフォーマンスの現場で、表現力を拡張するツールとして注目を集めています。
- 開発コンセプト:
音の位置ではなく「運動」にフォーカスした空間処理を実現するために開発 - ジェスチャルプロセッサー:
動きの変化を“音として感じさせる”仕組みで、演奏的な操作にも対応 - 物理エンジン搭載:
粒子の動きに物理的なロジックを導入し、自然な音響変化を生み出す - 視覚重視のUI設計:
音の挙動を直感的に捉えられる3Dビューポートを標準装備 - リアルタイム処理志向:
パフォーマンス現場で使えるよう、操作遅延を最小限に設計 - アップデート継続中:
開発初期から機能追加や改善が続けられており、ユーザー描画機能なども追加
他の空間オーディオVSTとの違い
空間オーディオ系のVSTプラグインは数多くありますが、Frahmがユニークなのは“音の移動そのもの”をリアルタイムでコントロールできる点です。
多くのプラグインがリバーブや定位で空間性を演出するのに対し、Frahmは動きのある粒子を使って、時間と空間を融合した音響表現を実現します。
このように、Frahmは音を「配置する」のではなく「流動させる」ことで、聴き手に対して没入感や動的な音場を提供できる点が際立っています。
そのため、従来の空間処理では物足りなさを感じていたユーザーにとっては、新しい選択肢となります。
- 音源を物理的に動かす設計:
パンニングや定位ではなく、仮想空間内を移動する粒子で音を制御 - 視覚的に挙動を確認できる:
OpenGLビューポートでパーティクルの動きをリアルタイムに視認 - 10種類の力場アルゴリズム:
一般的な空間系エフェクトにないダイナミックな動きが作れる - ユーザー描画対応:
力場を自分で描ける自由度の高いシステムは他のVSTにはない独自機能 - ドップラー効果を最適化処理:
移動に伴う周波数変化をCPU負荷を抑えつつ表現可能 - サウンドの“動き”を演出できる:
固定的な空間感ではなく、動的で変化する音場構成が可能
Lese「Frahm」の価格
価格:$55.00
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。
Frahmの力場システムとは?音を動かす原理をやさしく解説
Frahmの中核にあるのが「力場(フォースフィールド)」と呼ばれるシステムです。
これは、仮想空間内の粒子に“どの方向に動くか”を指示するアルゴリズムの集合体で、まるで重力や風のように音の動きをコントロールします。
このことから、単に音の位置を設定するのではなく、「どの方向にどのスピードで動くか」「どんなパターンで軌道を描くか」といった運動そのものを音に反映できます。
視覚的にも変化が確認できるため、操作も直感的に行えます。
- ベクターフィールド制御:
粒子に対して常に方向ベクトルを与えるシステムで、音の動きに一貫性と自然さが生まれる - 10種類の力場アルゴリズム:
重力風・渦巻き・ノイズなど、多彩な動き方を選択可能 - クロスフェード機能:
異なる力場同士をミックスして、複雑な動きや移行も滑らかに表現 - メタパラメーター設定:
速度や移動軸、動作範囲など全体的な動き方をカスタマイズ可能 - 描画による力場生成:
ユーザー自身が力の方向や強さを視覚的に描いて指定することも可能 - 動きに応じた音響効果:
力場の変化に伴ってパンや音圧、ドップラー効果も変化し、音に生命感が宿る
力場(フォースフィールド)とは何か?音との関係性
Frahmにおける力場(フォースフィールド)は、音の動き方そのものを決定するアルゴリズムです。
粒子がどの方向に進むかを決める見えない「場」として機能し、音源に動きの命を吹き込む役割を果たします。
通常のエフェクトでは得られない、複雑で有機的なサウンドモーションが生まれるのは、この仕組みによるものです。
このように、音を“動かす”という概念の中心には、力場の設計があり、パラメータ次第で動き方も音の印象も大きく変化します。
視覚的な理解も伴うため、創造的な音響操作がしやすいのも魅力です。
- 方向と速度を決める“場”の役割:
粒子の移動方向を力場が制御し、その結果として音が動くように聞こえる - リアルタイムで変化する力の影響:
時間の経過やパラメータの調整により、動きも音も常に変化し続ける - 空間全体に動きを与える:
音を個別に操作するのではなく、空間に力を加えることで全体の流れを作る発想 - 抽象的な音表現を可能にする:
予測不可能な軌道や動きが、意図を超えた音楽的表情を生み出す - パラメータによる多彩な演出:
強さ、範囲、方向性などを調整することで、細やかな空間コントロールが可能 - 複数の力場をブレンド可能:
2種類のアルゴリズムを組み合わせることで、複雑で洗練された動きが設計できる
パーティクルが音に与える影響とは?
Frahmの音響処理の中核には「パーティクル(粒子)」の概念があります。
これは単なる視覚的な演出ではなく、それぞれの粒子が仮想音源として機能し、空間内を移動しながら音を発します。
粒子がどのように動くかによって、音の広がりや方向感、スピード感がすべて変化するため、音楽の印象に強い影響を与えます。
このように、パーティクルの配置や挙動を制御することで、音を点ではなく面や流れとして捉えることができるようになります。
音の“存在感”そのものが、動きによって演出されるのがFrahmの大きな魅力です。
- 個々の粒子が音源になる:
一粒一粒が独立した音を発し、全体で複雑な音響空間を形成 - 動きによって定位感が変わる:
移動速度や方向によって、パンニングや音圧の印象が常に変化する - 距離感と奥行きが表現できる:
遠ざかる・近づく動作により、立体感のある音場を作り出す - ドップラー効果が自然に適用される:
移動スピードに応じて、音の高さやタイミングがリアルに変わる - パーティクル数による密度調整:
粒子の数が多いほど空間が厚く、少ないとミニマルな質感になる - 複雑な音の流れを演出可能:
粒子を動かす力場と組み合わせることで、複雑な音響軌道を自在に作れる
クロスフェード機能で得られる音響効果
Frahmのクロスフェード機能は、2つの異なる力場アルゴリズムを滑らかに切り替えるための仕組みです。
単なる切り替えではなく、間をつなぐように音の動きが自然に変化していくため、演出の流れを壊さずに新たな動きを加えることができます。
このことから、単調になりがちな音のモーションに動的な変化を与えられ、楽曲全体の表情に奥行きが生まれます。
特にライブパフォーマンスやインスタレーションなど、リアルタイム性を重視する場面で効果を発揮します。
- 異なる動きを滑らかに融合:
風と重力、渦とノイズなど、異なる力場をブレンドして新しい動き方を作れる - 無音の切り替えが不要になる:
音の動きが連続的に変化するため、フェードイン・アウトの処理が不要 - リアルタイムに動きを調整可能:
操作中でもスムーズに移行でき、演奏や即興にも強い - 音の印象を自然に変えられる:
音の動きが変わることで、響きや定位感も違ったものに感じられる - 効果を視覚的に把握しやすい:
クロスフェードの進行状況がビューポートに反映されるため、操作が直感的 - 構造的な音作りに活用できる:
曲の展開に合わせて力場を変化させることで、構成に合わせた音響演出が可能
OpenGLによる3Dビューポートで「音の動き」を視覚化
Frahmの大きな特徴の一つが、OpenGLを用いた3Dビューポートによって、音の動き=パーティクルの挙動を視覚的に確認できることです。
これにより、音がどの方向へ進んでいるのか、どこに集まり、どこに広がっているのかを直感的に理解できます。
このおかげで、聴覚だけでは把握しづらい空間的な動きも、視覚的な補助によってイメージしやすくなり、調整や設計がしやすくなります。
音と動きが一致する感覚が得られるため、演奏感や制作体験にもリアリティが増します。
- 粒子の動きがリアルタイムで表示される:
どのような軌道で音が動いているかを目で見て把握できる - 視点操作が可能:
X/Yスライダーやマウス操作で空間の角度を自由に変更できる - 動きと音の関係を掴みやすい:
視覚と聴覚が連動することで、音響設計の精度が上がる - 力場の表示も選択可能:
どのエリアでどんな動きが起きているかを力場のベクトル表示で確認できる - 複雑な動きも整理して理解できる:
複数のパーティクルや力場が重なっても、ビジュアルが整理されているので把握しやすい - ライブ時のフィードバックにも有効:
視覚情報によってリアルタイム操作の反応をすぐに確認できる
3Dビューの操作方法と見どころ
Frahmの3Dビューポートは、音の動きを視覚的に捉えるだけでなく、操作性にも優れた設計がされています。
角度の変更や表示モードの切り替えなど、制作者が“空間のどこで何が起きているか”を直感的に把握できる工夫が施されています。
その結果として、パーティクルの動きや力場の影響範囲を正確に視認できるため、音の流れに合わせた精密なサウンドデザインが可能になります。
初めて触れる人でも、見た目から仕組みが理解しやすく、操作が迷いにくい点も魅力です。
- 視点を自由に動かせる:
マウスドラッグやX/Yスライダーで空間の見え方を自在に調整可能 - 表示モードの切り替えが可能:
通常表示のほかに「力場表示」モードでベクトルの動きを視覚化できる - パーティクルの挙動をリアルタイム確認:
速度・方向・密度などがそのまま画面上に反映される - 動きの変化がすぐに分かる:
力場やメタパラメーターの変更が即座にビューポートに反映される - 直感的なデバッグができる:
音の挙動に違和感がある場合も、視覚的に原因を見つけやすい - 操作の試行錯誤がしやすい:
動きや表示を見ながら自由に実験できるため、創作意欲を刺激する
カオスを視覚化するとは?実際の表示内容と使い方
Frahmでは、力場やパーティクルの動きによって生じる「カオス的な音の流れ」を、3Dビューポート上でリアルに視覚化できます。
複雑に交差する粒子の軌道や、力場のベクトルが作り出す不規則な動きは、視覚的にも非常にダイナミックです。
このような視覚情報が得られることで、音の動きが偶発的であってもコントロールの指針を得やすくなります。
また、動きの変化を事前に視覚的に予測できるため、より精密な設計や演出が可能になります。
- 力場の“見えない力”が見える:
表示モードでベクトル(力の向きと強さ)を視認でき、音の動きの予測がしやすくなる - パーティクルの乱れを確認できる:
複雑に動く粒子群の交差や集中を見て、音響の密度や分布を把握できる - 混沌と秩序のバランスが取れる:
意図的に“整った動き”と“無秩序な動き”を組み合わせることで、音に表情を加えられる - 設定の影響が瞬時に見える:
力場や速度、範囲を変更すると即座に動きが変化し、試行錯誤がしやすい - ライブや即興演奏にも強い:
予測不能な動きが視覚的に補完されるため、即時対応しやすい - 音の動きの“質感”を演出できる:
ただ動かすのではなく、動きのクセや傾向を視覚からコントロールできる
Frahmの音響モードと空間処理の仕組み
Frahmには、音の出力形式に応じて複数の空間処理モードが用意されています。
主に「ステレオ」「バイノーラル」「HQバイノーラル」の3種類があり、それぞれ用途に応じて選択可能です。
どのモードでも、粒子の動きに基づいた空間的な音の広がりを再現する点は共通しています。
このことから、リスニング環境や目的に合わせて最適な空間処理を選べる柔軟性があり、クリエイターの意図をより忠実に反映できる仕組みとなっています。
ヘッドホン、スピーカー、没入型音響のいずれにも対応可能です。
- ステレオモード:
従来のスピーカー出力に最適化され、左右の定位感を自然に再現 - バイノーラルモード:
ヘッドホン用に設計された立体音響処理。
頭内定位を超えた自然な空間感を再現 - HQバイノーラルモード:
バイノーラル処理の精度をさらに高め、音の位置や距離感が一層リアルになる - 切り替えが即時反映される:
モードの変更による音響の違いをすぐに確認できるため、ミックス判断がしやすい - 用途に応じた使い分けが可能:
リスニング環境や作品の目的に応じて、最適な空間処理を選択できる - 全モードがリアルタイム処理対応:
パフォーマンス中の切り替えや微調整にも対応し、柔軟な演出が可能
バイノーラルモードの設定と効果
Frahmのバイノーラルモードは、ヘッドホン環境で真価を発揮する立体音響処理機能です。
粒子の動きに応じて、音が頭の周囲を移動しているように感じられるため、強い没入感とリアリティを演出できます。
設定は簡単で、出力モードを「Binaural」に切り替えるだけで機能が有効になります。
このように、バイノーラルモードはリスナーに向けた直接的な空間演出手段として活用でき、楽曲や効果音に動きを加えたい場面で特に効果的です。
立体的な広がりと方向感を強調したい制作物において、大きな武器になります。
- 立体的な音像を再現:
頭の前後・上下・左右など、あらゆる方向から音が聞こえるように配置可能 - ヘッドホン専用に最適化:
バイノーラル処理はヘッドホン視聴時に最も自然に機能するよう設計されている - 設定はワンタッチで切り替え可能:
出力形式のメニューから「Binaural」を選ぶだけで適用される - 粒子の動きが音に直結:
視覚的に動かした粒子の位置がそのままリスナーの聴こえ方に影響する - 自然なドップラー効果も反映:
移動速度に応じて音のピッチや距離感も変化する - VRや映画音響にも対応:
空間的な没入感が求められるコンテンツ制作において高い効果を発揮する
ステレオモードとの違いと使い分け方
Frahmでは、バイノーラルモードだけでなく、従来のステレオ環境に対応したモードも利用可能です。
ステレオモードは、左右のスピーカーやモニターでの再生を前提としており、パンニングや左右の広がりを自然に表現できます。
このように、ステレオとバイノーラルの違いは、リスニング環境と目的に応じた“空間の感じ方”にあります。
どちらのモードもFrahmのパーティクルシステムと連動して動作するため、同じ素材でも聞こえ方が大きく変わるのが特徴です。
- 出力対象の違い:
ステレオはスピーカー向け、バイノーラルはヘッドホン向けに設計されている - 空間の広がり方:
ステレオは左右方向の広がりが中心だが、バイノーラルは前後・上下も加わる - リスナーの没入感:
バイノーラルは「音に包まれる」感覚が強く、ステレオはより自然で定位のはっきりした印象 - ミックスでの判断基準:
スピーカーでの再生を想定した楽曲や映像ではステレオ、ヘッドホンでの体験重視ならバイノーラルが適している - 出力切り替えが簡単:
Frahm内の設定メニューからワンクリックで変更でき、比較がしやすい - 状況に応じて併用も可能:
用途に応じて複数のモードを切り替えたり、同じ素材を別モードで再レンダリングすることも可能
HQバイノーラルって何が違うのか?
Frahmの「HQバイノーラル」モードは、通常のバイノーラル出力をさらに高精度に処理する上位モードです。
よりリアルな音像定位や繊細な距離感の表現が可能になり、特に没入感を重視する作品や、細部まで緻密に作り込みたいプロジェクトに最適です。
このように、HQバイノーラルは“高解像度な空間音響”を求めるユーザーに向けた設計であり、環境音、サウンドスケープ、VRコンテンツなど、立体的な音の再現性が求められる場面で威力を発揮します。
- 音の定位精度が向上:
通常モードよりも、音の移動や位置がよりはっきりと感じられる - 距離感の表現が滑らか:
近づく・遠ざかる動きの変化がより自然に聴こえる - 微細な動きにも反応:
パーティクルのわずかな移動も空間表現として反映されるため、繊細な演出が可能 - 複雑なサウンドでも埋もれにくい:
粒子数が多いシーンでも一音一音の定位が明瞭に保たれる - 再現性の高さが魅力:
サウンドの細部にまでこだわるプロフェッショナルな用途にも対応 - CPU負荷はやや高め:
高精度処理のため処理負荷は上がるが、その分だけ得られる効果は大きい
Doppler Shiftの効果とは?Frahmでの応用を詳しく解説
Frahmは、音の移動にともなう「Doppler Shift(ドップラー効果)」をリアルタイムで処理できる数少ないプラグインの一つです。
これは、音源がリスナーに近づいたり遠ざかったりすることで生じる音の周波数変化を再現する技術で、現実の物理現象に基づいた自然な音響演出が可能になります。
その結果として、音が空間内を移動する動きにリアリティが加わり、より臨場感のあるサウンドデザインが実現します。
特にゲームや映像音響、臨場感の強い音楽制作で有効です。
- 音の高さが動きに応じて変化:
近づく音は高く、遠ざかる音は低く聴こえる自然な変化を再現 - Frahmでは粒子ごとに個別処理:
すべてのパーティクルに対して個別にドップラー演算を行うため、細かく動く音も精密に表現可能 - 他のプラグインよりも低負荷で動作:
独自の処理設計により、複雑なドップラー演算も軽量に実現 - リアルな空間感を演出:
実際の物理挙動に近いため、映像やゲームと組み合わせた際の没入感が高い - 演出効果の幅が広がる:
スピード感や緊張感を与えたいシーンなど、音の動きにドラマを加えられる - 自動制御と手動調整の併用が可能:
アルゴリズムによる自動動作と、ユーザーによるパラメータ調整が両立できる柔軟性がある
Frahmの使い方:操作性とパフォーマンス機能をチェック
Frahmは、音響設計に必要な複雑さを持ちながらも、直感的に操作できる設計がされています。
とくにパフォーマンス用途を想定した機能が充実しており、リアルタイムでの音の動きや挙動をコントロールしやすく、ライブや即興演奏の場でも威力を発揮します。
このように、視覚的な操作性とパフォーマンス志向の設計が両立しているため、「試しながら作る」「演奏しながら動かす」といったクリエイティブな使い方が可能になります。
実験性と実用性を兼ね備えたインターフェースが魅力です。
- リアルタイム操作に最適化:
マウスやMIDIコントローラーで直感的に動きを変更でき、即時反映される - ビューポートが常時更新:
パーティクルの変化が視覚的に反映され、動きと音を同時に把握できる - 操作による音の変化が分かりやすい:
力場やメタパラメーターを変えることで、音の印象が即座に変化 - パフォーマンス中の安定性が高い:
高負荷処理でも破綻しにくい構造で、演奏中の挙動も滑らか - レイテンシーが少なく反応が速い:
操作と音の反映がタイムラグなく行われるため、演奏の一部として扱える - カスタマイズ性の高いUI:
ウィンドウサイズの変更や表示モードの切り替えが自由で、環境に合わせやすい
Freeze機能や内部バッファ調整の使いどころ
Frahmには、リアルタイムで動くパーティクルの挙動を一時的に固定できる「Freeze(フリーズ)機能」や、内部オーディオバッファを細かく調整できる仕組みが備わっています。
これらは主にライブパフォーマンスや、意図的に音の動きを止めて強調したい場面で活用されます。
このような制御機能を活用することで、空間演出の緩急をつけたり、特定の瞬間を「静止画」のように扱ったりと、音の動きを戦略的に扱えるようになります。
即興演奏やサウンドアートにも向いた自由度の高いコントロールが可能です。
- Freeze機能で動きを停止:
任意のタイミングで粒子の動きを止め、音の配置を一時固定できる - 一時的な静止で演出に緊張感を:
動きの多いサウンドの中で、動きを止めることで逆に存在感を際立たせることができる - 内部バッファの手動調整が可能:
再生中の音を保持・再利用する設定ができ、音の質感や応答性をコントロールできる - 再生を滑らかに維持できる:
フリーズやバッファ操作によって音が破綻しないよう配慮された設計 - 音の断片化・重ねがけに対応:
凍結中に別インスタンスを動かせば、多層的な音響構成が可能になる - ライブ表現の幅が広がる:
動きの中に“止まる瞬間”を作ることで、緩急ある演出を即興でコントロールできる
自分だけの力場を描く!Frahmのカスタム描画機能
Frahmのバージョン1.1で追加された「Userアルゴリズム」は、ユーザー自身が力場を“描いて”作成できる機能です。
専用のエディタ上で力の方向や強さを手描き入力することで、動きのルールを自由にカスタマイズできるようになりました。
このことから、従来のプリセット的な動きだけでなく、作り手の意図や創造性に基づいた動きを直接設計することが可能になります。
感覚的に操作できるため、サウンドデザインにおける表現の幅が大きく広がります。
- 専用エディタで自由に描画可能:
グリッド状の画面上でマウスやタッチパッドを使って力のベクトルを描ける - 力場を3Dで構築できる:
複数のスライスに分けて奥行きのある力場を層として描き、立体的な動きを作成 - 直感的な操作性:
描いた通りに粒子が動き、結果が即座に視覚・聴覚に反映される - 独自性の高い動きを設計可能:
プリセットにない複雑な動きを自分のスタイルに合わせて作れる - 保存と再利用ができる:
一度作成した力場は保存して他のプロジェクトやインスタンスでも利用可能 - 即興演奏や実験音楽にも最適:
その場で描き直して反映できるため、ライブ中の変化演出にも強い
Userアルゴリズムとは?1.1で追加された新機能
Frahmのアップデート1.1で実装された「User」アルゴリズムは、これまでの力場アルゴリズムと異なり、ユーザーが自由に動きのロジックを設計できる機能です。
専用の描画エディタを使って、力の方向や強度を視覚的に定義できるため、従来の数学的な設定とは異なる直感的なアプローチが可能になりました。
このおかげで、独自性の高い空間演出が手軽に行えるようになり、サウンドデザインの創造性が大きく広がります。
あらかじめ用意された動きに縛られることなく、自分だけの音の動きを自由に形にできる点が最大の魅力です。
- 自由な力場設計が可能:
プリセットではなく、自分の感覚に合わせてパーティクルの動きを構築できる - 描画エディタによる操作:
マウスやペンでベクトルを描き、力の流れを直接設定できる - 3D的な表現に対応:
複数のスライス(断面)を切り替えながら、奥行きのある力場を設計できる - 実験的な動きにも対応:
パターン化された動きではなく、ランダム性や複雑さを自由に加えられる - 設定の保存・読み込みが可能:
作成した力場はプリセットとして保存でき、他プロジェクトでも活用可能 - インスピレーションを刺激する機能:
絵を描くように音を動かす新感覚の制作体験が得られる
描画モードの操作と実践的な使い方
Frahmの描画モードは、ユーザーが力場のベクトルを“手で描く”ように設定できるインターフェースです。
操作は非常に直感的で、専用エディタ内でベクトルの方向や強さをグリッド上に描き込むだけ。
さらに、Z軸方向(奥行き)にスライスを切り替えることで、3次元的な構造も構築できます。
このように、描画モードを活用することで、音の動きを完全に自分のイメージ通りに設計することが可能になります。
手描きの操作と音の反応が直結するため、偶発的な面白さと緻密な調整の両立ができます。
- エディタ上でマウス描画操作:
力の向きや強さをグリッドにドラッグするだけで設定できる - Zスライス切り替えで奥行きを設計:
複数の平面を積み重ねるように、立体的な力場を構成できる - 動きの微調整がしやすい:
一部だけを書き換える、強さを弱めるなど、細かな操作が可能 - リアルタイム反映が可能:
描いた内容が即座に粒子の動きに反映され、音で確認できる - 複数プリセットの切り替えも容易:
複数の自作力場を保存し、即座に切り替えて比較できる - 実験音楽や空間演出との相性が抜群:
視覚的に“構築された動き”がそのまま音になるため、アート性の高い表現が可能
動作環境
Frahmは、主要なDAW(Digital Audio Workstation)との高い互換性を備えており、プラグイン形式も豊富に用意されています。
VST3、AU、AAXに対応しているため、Windows・macOS両方の環境で安定して動作します。
さらに、インテル/Appleシリコン両方のMacでもサポートされているため、幅広いユーザーに対応可能です。
このように、導入が簡単で動作も安定しているため、普段使っているDAWにすぐに取り込んで、音響制作の一部として活用できます。
複数インスタンスの使用にも対応しており、大規模なプロジェクトにも柔軟に対応できます。
- 対応プラグイン形式:
VST3、AU、AAXをサポートしており、Logic Pro、Ableton Live、Cubase、Pro Toolsなどで利用可能 - マルチOS対応:
Windows(64bit)とmacOS(Intel/Apple Silicon)に対応 - 複数インスタンス対応:
同一セッション内で複数のFrahmを立ち上げ、音の動きを重ね合わせることが可能 - MIDIコントロールに対応:
一部のパラメーターはMIDIマッピング可能で、外部操作も柔軟に行える - 軽量で安定した動作:
高負荷な空間処理をしながらも、DAWの安定性を損なわない設計 - セットアップもシンプル:
インストール後すぐに使用可能で、複雑な設定不要
まとめ:Frahmが切り開く、新しい空間音響の世界|DTMプラグインセール
今回の記事では、Leseの空間音響プラグイン「Frahm」について詳しくご紹介しました。
以下に要点を整理します。
- Frahmは、粒子の動きに基づいた立体音響を実現する革新的なVST/AUプラグイン
- 力場アルゴリズムによって、音を空間内で自在に動かすことが可能
- OpenGLによる3Dビューポートで、音の動きや力の影響を視覚的に確認できる
- バイノーラル/ステレオ/HQバイノーラルなど複数の音響モードに対応
- 自分で力場を描けるUserアルゴリズムにより、自由な音の動きの設計が可能
- DAWとの互換性も高く、ライブや制作の即戦力として活躍できる
このように、Frahmは“音を配置する”から“音を動かす”時代へと進化させるツールです。
楽曲制作はもちろん、映像音響、インスタレーション、VRコンテンツなど、あらゆるシーンで空間音響の表現を豊かにしてくれます。
ぜひ、あなたの制作環境にもFrahmを取り入れて、これまでにない音の動きを体験してみてください。
価格:$55.00
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。






