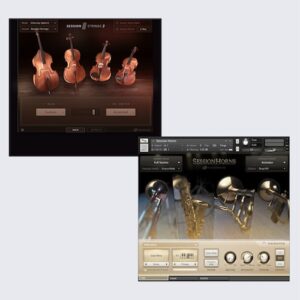もっと攻めた音が作れたら…
音に個性が足りない気がする
そんな風に感じたことはありませんか?
しかも、エンベロープフォロワーとオーディオモジュレーションの2つの制御で、音の動きを“演出”できるのが魅力。
この記事では、Driverの基本から、音作りにどう活かせるかまでを丁寧に解説します。
「使ってみたいけど難しそう…」という方でも安心して読み進められる内容です。
ぜひ最後までチェックして、あなたの音に“破壊と創造”の一滴を加えてみてください。
価格:$49.00
>>>その他Native Instruments製品はコチラ
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。
Driverとは何か?その特徴と他エフェクトとの違い

Driverは、Native Instrumentsが手がけたエフェクトプラグインで、フィルターとディストーションを組み合わせたサウンド変化が魅力です。
従来のディストーションとは異なり、単に音を歪ませるだけでなく、音に立体感や動きを加えることができます。
音の強弱に反応してエフェクトが変化するエンベロープフォロワーや、オーディオモジュレーションによるリアルタイム制御が可能な点が大きな特長です。
そのため、Driverは「音を加工するエフェクト」というより、「音を操作して演出するツール」と言えます。
フィルターとディストーションの融合:
カットオフ周波数と共に歪みが変化し、音に複雑な質感を加えることができる。
フィルターはローパスとノッチの2種類を搭載。
エンベロープフォロワー:
入力された音量の変化に合わせて自動的にフィルターや歪みの効果が動く。
演奏の強弱を活かした動的なサウンド作りが可能。
オーディオ/オシレーターモジュレーション:
別トラックの音(サイドチェイン)や内蔵オシレーターを使って、周期的または入力に応じた変化を与えられる。
リズムに連動した効果も簡単に実現。
プリセットとユーザー設定の保存:
即戦力となるFactoryプリセットと、自分で作った設定を保存できるUserプリセットの切り替えが可能。
実験的な設定も気軽に保存・再呼び出しできる。
使いどころの幅広さ:
ドラム、シンセ、ボーカル、ベースなど、どのトラックにも使用可能。
微細な変化から破壊的なエフェクトまで幅広く対応。
Driverはどんなエフェクト?基本概要と特徴を解説

Driverは、Native Instrumentsが開発したディストーションとフィルターを組み合わせたマルチエフェクトです。
通常の歪み系エフェクトとは異なり、単に音を荒くするのではなく、フィルター処理とモジュレーション制御によって、音の質感を自由自在に操ることができます。
シンプルな構造ながらも、極端な加工から繊細な変化まで対応できる柔軟さがあり、音楽ジャンルを問わず活躍するツールです。
その結果として、Driverは初心者にも扱いやすく、上級者には音作りの幅を広げる存在として重宝されています。
2つのフィルタータイプ:
12dBのローパスフィルターとノッチフィルターを切り替えて使用可能。
ローパスは高域を削って丸みを与え、ノッチは特定帯域を切り取ることで空間を演出。
パワフルなディストーション:
単純な歪みではなく、フィルターと連動したダイナミックな歪みが特徴。
音に芯とインパクトを加えるだけでなく、音像に厚みを持たせることもできる。
視認性の高いインターフェース:
直感的なUI設計で、各パラメーターの変化が視覚的に分かる。
マウスオーバーで数値も表示され、初心者でも扱いやすい。
柔軟なモジュレーション:
エンベロープフォロワーやAM機能により、音に動きを加える演出が可能。
DAWのオートメーションに頼らず、自然な変化を作り出せる。
サイドチェイン対応:
外部音源をトリガーとして使えるSC(サイドチェイン)入力を搭載。
他トラックの音と連動したエフェクト変化が可能。
他のディストーション系エフェクトと何が違うのか

一般的なディストーション系エフェクトは、「歪ませる」ことに特化しており、サウンドに荒々しさやアタック感を与えるのが主な目的です。
しかしDriverは、ディストーション単体ではなく、フィルターとモジュレーションを一体化させた設計で、音のトーン変化や動きも含めて“デザイン”できる点が大きな違いです。
その影響で、Driverは歪みの量や質だけでなく、タイミングや周波数成分にまでアプローチでき、結果としてより創造的な音作りが可能になります。
エンベロープフォロワーによる動的な変化:
入力音の音量に応じて、フィルターや歪みのかかり具合が自動で変化する。
演奏の強弱にリンクした自然なエフェクト効果を生み出せる。
Audio / Oscモードの切替が可能:
外部のオーディオ信号(Audio)や内蔵オシレーター(Osc)を使って、ディストーションやフィルターに周期的な変化を与えられる。他のディストーションにはない柔軟性。
フィルターとの一体化設計:
DISTOノブ単体ではなく、カットオフやレゾナンスとの連動が音の変化を作る鍵。
そのため、単調な歪みではなく、トーンに深みが出る。
細かな設定が直感的に操作可能:
Lag(変化の滑らかさ)やClip Cut(モジュレーション信号の強調)など、特殊なパラメーターも用意。
微調整を感覚的に行える。
プリセットの多彩さと拡張性:
ジャンルに合わせた多くのプリセットが初期搭載されており、さらにユーザー自身で自由に作成・保存・管理ができる。
既存エフェクトと違い“自分用”に育てられる。
Native Instruments「Driver」の価格

価格:$49.00
>>>その他Native Instruments製品はコチラ
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。
Driverの基本的な使い方と導入方法

Driverは、VSTやAUプラグインとしてDAWに読み込むことで使用できます。
導入はとてもシンプルで、Native Instruments製品に共通する「Service Center」や「Native Access」を通じてインストールと認証を行います。
一度セットアップすれば、各トラックにインサートしてすぐに使用でき、プリセットを読み込むだけでも十分にパワフルな音作りが可能です。
そのため、複雑な初期設定なしで直感的に使い始められる点が、Driverの大きな魅力です。
- インストール方法:
Native Instruments公式サイトまたはKOMPLETEシリーズに含まれるDriverをダウンロードし、Native Accessでインストール・アクティベートを行う。 - DAWでの立ち上げ:
インストールが完了したら、DAWのプラグイン一覧から「Driver」を選択し、任意のトラックにインサート。
すぐに使用可能。 - 初回起動時のプリセット読み込み:
画面上部のメニューバーからプリセットを選択。
Factory(工場出荷)とUser(自作)を切り替えて保存・呼び出しが可能。 - 音が出ない場合の確認ポイント:
Driverはモジュレーションの影響で音が極端に変化するため、出力レベルやフィルター設定がゼロになっていないか確認が必要。 - ライセンスとバージョン管理:
Native Accessで常に最新バージョンへアップデート可能。
複数PCでの使用にはライセンス管理が必要になる場合がある。
Toneセクションの詳細と音作りの変化
Driverの上段に配置されたToneセクションは、フィルターとディストーションのコア部分であり、音の基本的なキャラクターを決定する重要なパラメーターが揃っています。
特に「FREQ(カットオフ)」と「DISTO(ディストーション量)」は、Driverならではの“音を変形させる力”を体感できる部分です。
音の加工と破壊を両立させたい場面で非常に頼りになります。
このことから、Toneセクションの理解はDriverを使いこなす第一歩と言えます。
INPUT(インプット):
入力音の音量を調整するノブ。
ここで信号を持ち上げることで、後段のディストーションがより強く反応する。
RES(レゾナンス):
フィルターのカットオフ周辺の周波数を強調する。
値を上げると金属的なピークが生まれ、サウンドに個性を加えることができる。
FREQ(カットオフ周波数):
フィルターの中心となる周波数を指定。
動かすことで音の明るさやこもり具合を大きく変化させられる。
DISTO(ディストーション量):
歪みの強さを調整。
低く設定すれば温かみのあるサチュレーション、高くすれば荒々しい破壊的な音になる。
COLOR(トーンの色味調整):
歪みのキャラクターを変更するノブ。
左に回すとこもった音に、右に回すと明るく攻撃的な音になる。
LPF / Notch(フィルタータイプ切替):
ローパスは高域を削って滑らかな音に。
ノッチは特定の帯域をくり抜くことで独特な空間的響きを加えられる。
OUTPUT(アウトプット):
最終的な出力音量を調整。
インプットやディストーションで音が大きくなるため、ここで適切に整える。
フィルターのFREQとRESが与える音の印象
Driverのフィルター部分は、サウンドの明るさや存在感をコントロールする上で欠かせないパラメーターです。
中でもFREQ(カットオフ)とRES(レゾナンス)は、音のキャラクターを大きく左右します。
FREQは「どの帯域を通すか」を決める役割があり、RESはその帯域周辺をどれだけ強調するかを決めるため、組み合わせ次第でサウンドの印象が劇的に変化します。
このように、フィルターをうまく活用することで、シンプルな音にも奥行きや動きを加えることができます。
FREQ(カットオフ周波数)の役割:
左に回すと高域が削れ、音がこもった印象に。右に回すと明るく抜けの良い音になる。
オートメーションやモジュレーションで動かすことで、ダイナミックなフィルターエフェクトを作り出せる。
RES(レゾナンス)の役割:
FREQで設定した周波数周辺を強調する。少し上げるだけで“ピーク”が生まれ、シンセっぽいキャラクターに変化。
高くしすぎると自己発振して高音が鋭くなるため、扱いには注意が必要。
FREQとRESの連動による音の変化:
FREQを動かしながらRESを高めに設定すると、”ワウ”のような印象的なフィルター効果が得られる。
演出として使いたいときに最適。
モジュレーションとの相性が抜群:
FREQやRESにエンベロープフォロワーやAMを適用すると、演奏や外部音源に合わせた動的な音の変化が生まれる。
機械的でない“人間っぽい”サウンド作りが可能。
DISTOとCOLORノブで作る破壊と艶
Driverのディストーションは、単なる歪みではなく、音の密度・質感・迫力までもコントロールできる奥深いパラメーターです。
DISTOノブで歪みの量を調整し、COLORノブでそのキャラクターを細かく調整することで、「音を太くする」「空気感を変える」「破壊的なエフェクトをかける」など、目的に応じた音作りができます。
そのため、単調なサチュレーションや激しいノイズとは一線を画した、立体的で表情のあるサウンドに仕上げることが可能です。
DISTO(ディストーション量):
左に寄せると軽いサチュレーションになり、自然な温かみを与えられる。
右に回すにつれて倍音が増え、激しい歪みが加わる。中間設定での“ジリジリ感”もDriverならでは。
COLOR(歪みのトーン調整):
左に回すと低域が強調され、ダークでこもった印象に。
右に回すと高域が持ち上がり、明るく鋭い音になる。サウンドの抜け感や攻撃性を微調整できるポイント。
DISTOとCOLORの組み合わせ:
たとえばDISTOを高く、COLORを右に振ると破壊的なノイズ系サウンドに。
逆にDISTOを中程度にしてCOLORを左寄りにすれば、太くて落ち着いたトーンになる。
フィルターとの連携で深みが増す:
DISTOだけでなく、FREQやRESとの組み合わせによって、歪みが音の一部として溶け込むような自然な仕上がりに。
音の“芯”を作るのに最適。
エンベロープフォロワーの仕組みと実践活用
Driverのエンベロープフォロワーは、入力された音の音量変化に反応して、フィルターやディストーションの効果を“動かす”ことができる非常に強力なモジュレーション機能です。
いわば、音の強弱に合わせてエフェクトが自動で変化する仕組みで、演奏の抑揚に連動した自然なサウンドが得られます。
これにより、DAWのオートメーションを描かずとも、ダイナミックな音作りが可能になります。
このおかげで、シンプルなループや一定のリズムに生命感を吹き込むことができます。
入力モード(IN / SC):
INでは現在のトラックの音量に応じて反応。
SC(サイドチェイン)を選ぶと、別トラックの音量に反応するようになり、他の楽器と連動した複雑な動きが可能になる。
SMOOTH(スムーズ):
エンベロープの反応速度を調整するノブ。
左に回すと変化がゆっくりになり、右に回すと素早く反応する。
グルーブ感や反応の鋭さを調整できる。
RELEASE(リリース):
エンベロープ効果が終わるまでの時間を設定。
長くするとじわっと効果が続き、短くするとすぐに戻る。
音の余韻やタメを演出したいときに活用できる。
FREQ / DISTO への適用:
エンベロープはフィルターと歪みに個別に適用可能。
たとえば、音が大きくなったときだけ歪ませたり、逆に音が小さいときだけカットオフを上げるといった動的な音作りができる。
Envelope Followerはどんな動きをするのか
Envelope Follower(エンベロープフォロワー)は、Driverの中でもとくに“動き”を生み出す要となるモジュレーション機能です。
この機能は、入力された音の音量変化をリアルタイムで検出し、その変化に応じてフィルターやディストーションのパラメーターを動かす役割を担います。
音の抑揚がそのままエフェクトに反映されるため、静的な設定では得られない“音の表情”を演出することができます。
その結果として、単調だったサウンドにダイナミズムと有機的な動きが加わります。
音量に応じた自動変化:
入力されたオーディオの大きさをリアルタイムで読み取り、設定されたパラメーターに比例して効果を加える。
人の手でオートメーションを書かなくても抑揚のある変化が生まれる。
正極/逆極の切り替え:
+(プラス)モードでは、音量が上がるとエフェクトも強くなり、−(マイナス)モードではその逆になる。
この切り替えで音の盛り上げや抑制の演出を自在にコントロールできる。
FREQ / DISTOスライダー:
それぞれのパラメーターに対し、エンベロープがどの程度影響するかを設定できるスライダーを搭載。
上げれば影響が強くなり、下げると効果が減少。繊細な調整が可能。
演奏とリンクした“音の表情”:
たとえば、強く叩いたキックに合わせてフィルターが開く、静かなパートでディストーションが控えめになるなど、演奏に反応する“生きた音”を作るのに最適。
SC(サイドチェイン)入力で何ができる?
DriverのEnvelope FollowerおよびAudio Modulationセクションでは、IN(インプット)だけでなく、SC(サイドチェイン)入力を選ぶことができます。
サイドチェイン入力を使うと、別のトラックの音をトリガーとしてDriverのエフェクトを動かすことができるため、複雑でリズミカルな音作りが可能になります。
特に、他のトラックと連動させて「音がぶつからないように調整したい」といったシーンに非常に有効です。
このように、SC機能を使いこなすことで、Driverはよりインタラクティブなサウンドデザインツールへと進化します。
別トラックからのモジュレーション制御:
Driverを挿したトラック以外の音を入力源にできる。
たとえばキックの音量に反応して、ベースのフィルターを開閉させるなど、パート間の連動が可能。
リズムに合わせた効果的な変化:
キックやスネアのようにリズミックな音をトリガーにすることで、Driverのエフェクトが一定のタイミングで動き、グルーヴ感を強化できる。
複雑なダッキング表現:
コンプレッサーのように音を単純に下げるのではなく、ディストーションやフィルターの効果を“避けるように”動かすことができる。
音量変化とは違った立体的な表現が可能。
非同期な音変化で予測不能な演出に:
トリガー音と加工対象の音が異なる場合、想定外の効果が得られることもある。
これにより、偶発的でクリエイティブなサウンドも生まれる。
Audioモードで使える設定と音の傾向
DriverのAudio Modulationセクションには「Audio」モードがあり、入力されたオーディオ信号そのものをモジュレーションソースとして使用することができます。
これにより、外部音源の細かい波形やリズムの変化をリアルタイムで捉え、それをフィルターやディストーションに直接影響させることが可能になります。
モジュレーションがサウンドの一部として融合するような効果を得られるため、自然で複雑な音の変化を演出したい場面に適しています。
その影響で、Audioモードは“環境音やノイズすら楽器化できる”ような柔軟性を持っています。
Input(IN / SC):
モジュレーション元として、自トラック(IN)か別トラック(SC)を選択できる。
SCにすることで、他のトラックの音に反応した動きを演出できる。
Clip Cut(クリップカット):
モジュレーション信号の波形をクリップして歪ませる。
高めに設定すると、より荒々しく、アグレッシブな音の揺れ方になる。
Lag(ラグ):
モジュレーション信号の変化速度を滑らかにする機能。
設定値を上げるとゆるやかな波のような変化になり、下げるとカクカクした反応になる。
FREQ modulation(カットオフ変調量):
入力音の波形でフィルターのカットオフを動かす量を調整。
グルーヴ感や空間の広がりを生み出す際に活用される。
DISTO modulation(歪み変調量):
オーディオ信号に応じてディストーションのかかり方を変化させる。
ダイナミックな歪み効果や、予測不能な音の動きが得られる。
Oscモードの特徴とエンベロープとの組み合わせ
DriverのAudio Modulationセクションには、Audioに加えてOsc(オシレーター)モードが用意されています。
このモードでは、内蔵のサイン波オシレーターをモジュレーションソースとして使用することができ、周期的で安定したエフェクトの変化を生み出すことが可能です。
さらに、このオシレーターにエンベロープフォロワーを組み合わせることで、予測可能な動きと動的な変化をミックスした、より豊かなサウンド表現が実現します。
その結果として、揺らぎやうねりのある表現を安定してコントロールしつつ、音楽的な抑揚も自然に加えることができます。
Envelope(エンベロープ影響量):
オシレーターに対してエンベロープフォロワーの影響を加える。
左に回すと反転、右に回すと正方向の変化。センターでは無効になる。
これによりオシレーターの強さを入力音でコントロールできる。
Rate(オシレーター周波数):
サイン波の周期を決定するパラメーター。
遅くすればゆったりした揺らぎ、速くすれば細かい震えや高周波モジュレーションが得られる。
Range(レートの範囲設定):
Rateの動作範囲をLO(0.03Hz〜26Hz)とHI(2Hz〜15.8kHz)で切り替える。
LOではLFO的、HIではFM的な過激な変調が可能。
FREQ modulation(カットオフ変調量):
Oscモードの出力でフィルターのカットオフを揺らす。
一定の周期でフィルターが動くことで、リズムやテンポに合わせた変化が得られる。
DISTO modulation(歪み変調量):
オシレーターの信号でディストーションの強さを周期的に変化させる。
これにより、歪みが“脈打つ”ような効果や、音の波打つような質感が生まれる。
Driverのおすすめプリセットとカスタム方法
Driverには、Native Instrumentsが用意した多彩なFactoryプリセットが多数搭載されており、ジャンルや目的に応じた音作りがすぐに試せるようになっています。
また、自分で作った設定をUserプリセットとして保存することもできるため、制作スタイルに合わせた“マイエフェクト”として育てていくことが可能です。
音作りを繰り返す中で、「これは使える」と思った設定は迷わず保存しておくのがおすすめです。
このように、プリセットを活用すれば、Driverの理解と応用の幅が一気に広がります。
Factoryプリセットの選び方:
画面上部のメニューバーからプリセット一覧を開き、ジャンル別・効果別に分かれたFactoryプリセットを確認できる。
軽めのフィルター系から過激なディストーション系までバリエーション豊富。
Userプリセットの保存方法:
メニューバー左のFileメニューから「Save As…」を選択し、任意の名前をつけて保存。
これにより、いつでも自分だけの設定を再呼び出しできるようになる。
プリセットの整理・管理:
Fileメニュー内の「Show User Preset Folder」からプリセットの保存先を開ける。
ここでファイル名を変更したり、不要なプリセットを削除したりと、整理も簡単。
プリセットの呼び出しと切り替え:
プリセットの左右矢印ボタンで順送り・逆送りができる。
アイディア出しやサウンド比較の際に非常に便利。
カスタムとプリセットの併用:
Factoryプリセットをベースに微調整し、自分好みにカスタムして保存すれば効率的。
複数の“お気に入り設定”を作っておくと、制作スピードも格段に上がる。
Factoryプリセットの傾向と選び方
Driverには、あらかじめ用意された多数のFactoryプリセットが収録されており、ジャンルや目的に応じて即戦力として活用できる構成になっています。
プリセットは「歪み重視」「フィルター中心」「モジュレーション強め」など、効果の方向性ごとに個性が分かれているため、使用シーンに応じて選ぶのがコツです。
細かい設定が苦手な方でも、まずはプリセットを試すことでDriverの可能性を体感できます。
このことから、まずは用途別の傾向を押さえておくと、制作に活かしやすくなります。
フィルター系プリセット:
ローパスやノッチフィルター中心の設定で、音を柔らかくしたり、空間的にくり抜いた印象を作れる。
アンビエントやポップ系に向いている。
ディストーション系プリセット:
DISTOノブが高めに設定されており、音を太く荒々しく仕上げる。
EDMやインダストリアル、ハードロックなどに適している。
モジュレーション重視プリセット:
Envelope FollowerやAudio Modの影響が大きく設定されており、音が絶えず変化するような動きが加わる。
実験的なサウンドやエレクトロ系にぴったり。
軽めの味付けプリセット:
極端な変化は避け、トーン補正や微細なフィルター処理を中心に構成されている。
ボーカルやアコースティック素材などに自然に馴染む。
音のインスピレーション用プリセット:
「これは何に使うんだろう?」と思わせるような個性的な音も多数収録されている。
思いがけない音作りのヒントやネタ出しに役立つ。
Userプリセットの保存・呼び出し・整理術
Driverでは、自分で作成した設定をUserプリセットとして保存し、いつでも呼び出して再利用することができます。
これは「一度作った理想の音を忘れずに残しておきたい」「曲ごとにお気に入りの設定を切り替えたい」といった制作現場で非常に役立つ機能です。
複数のバージョンを保存しておけば、音作りの比較検討や、リファレンス作成もスムーズに行えます。
このように、Userプリセットを活用することで、Driverを自分専用のサウンドツールとして育てていくことができます。
保存方法:
画面上部のFileメニューから「Save As…」を選択し、任意のプリセット名を入力して保存。
保存後はメニュー内の「User」タブに自動で追加される。
呼び出し方法:
Presetメニューをクリックし、「User」セクションから目的のプリセットを選ぶだけで即反映。
作った設定を何度でも使い回せる。
プリセットの管理フォルダを開く:
Fileメニューの「Show User Preset Folder」をクリックすると、保存先のフォルダが開く。
ここでプリセットファイルの並べ替えやリネームが可能。
削除・バックアップ方法:
不要なプリセットはフォルダ上で削除可能。
大切な設定は外部ストレージにコピーしておくと、万が一のPCトラブル時も安心。
分類の工夫で使いやすく:
ジャンルや用途に合わせて名前を付けておくと、後から探しやすくなる。
例:「warm_vocal」「aggressive_bass」「ambient_fx」など。
Driverを使った音作りの具体例と応用テクニック
Driverは、単なるエフェクトではなく「音の素材そのものを変化させる」ためのクリエイティブツールです。
そのため、使い方次第でドラムのアタック感を強調したり、ボーカルに表情を加えたり、シンセの空間的広がりを演出したりと、多様な活用が可能です。
実際の制作現場でも「この音、ちょっと面白くしたい」というときに重宝されるエフェクトで、シンプルな音にひと味加えるのに最適です。
このおかげで、Driverは初心者から上級者まで幅広く支持されています。
ドラムに使う:
スネアにDISTOを加えてパンチを強調し、FREQを動かして空間的な広がりを演出。
キックに使えばアタックの迫力とサブ感のコントロールが可能。
ボーカルに使う:
わずかなDISTOとCOLOR調整で声の“ザラつき”や存在感を強調。
フィルターで高域を軽くカットし、柔らかいニュアンスにもできる。
ベースに使う:
エンベロープフォロワーで歪みが弾き方に追従するように設定すると、人間らしい抑揚のあるベースサウンドが得られる。
Sub帯域を削りすぎないように注意。
シンセに使う:
OscモードでLFO的な動きを加えれば、シンセのパッドやリードが動きのある音に。
COLORを右に振ると、鮮やかなトーンに変化。
FX・環境音に使う:
ノイズやアンビエント素材にDISTOを加えると、予測不能なテクスチャサウンドに変化。
SC入力で他トラックに反応させると、リズムと連動した効果も可能。
ボーカル・ドラムにDriverを使うとどうなる?
Driverは、ボーカルやドラムといった“音の主役”にも強い効果を発揮します。
単なるエフェクトの追加ではなく、声や打楽器の質感を大きく変えることができるため、特に「印象を変えたい」「もっと個性的にしたい」というときにぴったりです。
使い方次第で“荒々しさ”にも“繊細さ”にも変化させられるので、ジャンルや楽曲の雰囲気に応じた調整がしやすいのも魅力です。
その結果、Driverを加えるだけで、ミックス全体にインパクトや深みを加えることができます。
ボーカルでの活用例:
- 軽くDISTOを加えることで、息遣いや声のザラつきが強調される。
ロックやインディ系に適したニュアンスが出せる。 - COLORを右に回すと高域が前に出て、声の輪郭が際立つ。
逆に左にするとマイルドな響きに変化。 - LPFフィルターで高域をなめらかにカットすれば、柔らかく温かみのある印象に。
バラードやLo-Fiにおすすめ。 - Envelope Followerを使えば、声の抑揚に合わせて自動でフィルターや歪みが変化。
自然な“表情”が生まれる。
ドラムでの活用例:
- キックにDISTOを強めにかけると低域に芯が生まれ、アタックも強調される。
EDMやテクノ系に最適。 - スネアにColorとRESを組み合わせて音の張りや金属感を追加。
ドラムが埋もれがちなミックスでも存在感を出せる。 - ハイハットにLPFとモジュレーションを組み合わせることで、リズムに動きを加える。
ループに生命感が宿る。 - SC入力を使えば、ボーカルやベースのアタックに合わせてドラムの音が変化する“連動感”のあるエフェクトが作れる。
キックやシンセで個性的な音を作る方法
Driverは、キックやシンセサイザーといったエレクトロニックな音素材との相性が非常に良く、既存の音にインパクトや動きを加えるのに最適です。
特に、DISTOやCOLORで音の質感をコントロールしながら、モジュレーションでタイミングや抑揚を与えることで、「音を変える」ではなく「音に表情を与える」という使い方が可能になります。
単調なループやフラットな音色に一工夫加えたいとき、Driverは非常に頼もしい存在になります。
このように、Driverを使えば「他と違う音」を生み出すための発想が自然と広がります。
キックでの活用例:
- DISTOを強めにかけることで、ローエンドにパンチと厚みが加わる。
特にクラブミュージックでの存在感アップに効果的。 - COLORをやや右寄りにすると、アタック部分がシャープになり、ミックス内でも抜けやすくなる。
- RESとFREQを動かすことで、808系キックにメロディ的な要素を加える演出も可能。
- AudioモードでハイハットのリズムをSC入力に設定し、キックのフィルターがそれに反応するように設定すれば、グルーヴ感のあるサウンドに。
シンセでの活用例:
- フィルターのFREQにモジュレーションをかけると、シンプルなシンセが複雑なモーションを持つ音に変化する。
- OscモードでLFO的に周期的変化を加えると、揺れやうねりが演出できる。
パッドや持続音に最適。 - COLORを調整することで、シンセの音色そのもののキャラクターを変化させることが可能。
- Envelope Followerを使って、演奏の強弱に応じてフィルターを開閉させれば、演奏に呼吸感が生まれる。
Driverを他のエフェクトと組み合わせて使う方法
Driver単体でも十分に強力なエフェクトですが、他のエフェクトと組み合わせることでさらに音作りの幅が広がります。
特に空間系やダイナミクス系と併用することで、Driverの特性を引き立てながら、ミックスに立体感や完成度をプラスできます。
目的に応じて前段に使うか後段に使うかで効果も大きく変わるため、順番や設定も工夫のしどころです。
このように、Driverは“単独使い”にとどまらず、“組み合わせることで真価を発揮する”タイプのエフェクトです。
リバーブ・ディレイとの併用:
- Driverを先に挿すと、歪んだ音が空間に広がり、荒々しいテクスチャになる。
アンビエントや実験系に効果的。 - リバーブやディレイをDriverの前に置くと、残響音だけが歪み、独特の浮遊感が得られる。
幻想的な空間演出におすすめ。 - フィルターで高域を削った後にリバーブをかければ、柔らかく落ち着いた響きになる。
コンプレッサーとの併用:
- Driverの後にコンプを入れると、歪みによって暴れた音を整えて聴きやすくできる。
ミックス全体へのなじみも良くなる。 - 逆にコンプを前段に入れてからDriverを使うと、音の密度が均一になり、歪みのかかり方が安定する。
- サイドチェインコンプと組み合わせれば、Driverで加工した音もリズムに合わせて自然に引っ込ませることができる。
EQとの組み合わせ:
- Driverで歪ませた後にEQで不要な帯域をカットすることで、クリアで狙い通りの音作りが可能になる。
- 特に中域のコントロールを意識することで、音が混み合ったミックスでも埋もれずにしっかり抜けてくる。
リバーブ・ディレイと組み合わせる音の広がり
Driverは歪みやフィルターで音の“質感”をコントロールするエフェクトですが、リバーブやディレイと組み合わせることで“空間”の演出まで可能になります。
この組み合わせは、音をただ加工するだけでなく、リスナーにとって“印象的な広がり”や“浮遊感”を与える手段として非常に有効です。
エフェクトのかけ順や設定次第で、同じ素材でもまったく違った立体感を生み出すことができます。
その結果として、ミックスに奥行きや深さを加えたいときに、Driverと空間系エフェクトは非常に心強い組み合わせになります。
Driver → リバーブの順番で使用:
- 歪みやフィルターで加工された音がリバーブ空間に広がるため、荒々しい音に幻想的な余韻がつく。
- インダストリアルやポストロック系のトラックで、ノイズや歪みを活かした“美しさと暴力の同居”を演出できる。
- フィルターで高域を抑えてからリバーブに送ると、柔らかい空気感が加わり、耳に優しい響きになる。
リバーブ → Driverの順番で使用:
- リバーブの残響音にDriverのDISTOをかけることで、空間そのものが歪んだような独特の広がりが生まれる。
- ハイパスフィルターと組み合わせて、リバーブ成分だけを加工し、アブストラクトなテクスチャを作ることも可能。
- まるで“リバーブの中にある別の音”のような演出ができ、映画音楽や環境音系でも効果を発揮。
ディレイとの併用:
- ディレイにDriverをかけると、繰り返される音が毎回少しずつ異なる表情になり、予測できない面白さが生まれる。
- モジュレーションを絡めることで、ディレイごとにフィルターが開閉するような複雑な動きも演出できる。
コンプレッサーとの組み合わせで得られる効果
Driverで加工した音は、そのままでも迫力ある仕上がりになりますが、コンプレッサーと組み合わせることで“輪郭の整理”や“音圧のコントロール”がさらに洗練されます。
特に、DriverのDISTOで荒くなった音や、モジュレーションによって動きのある音をコンプレッサーで整えると、ミックス全体のまとまりが向上します。
また、順番を入れ替えるだけでも効果が大きく変わるため、意図に合わせた使い分けが重要です。
このように、コンプレッサーとDriverの併用は“荒々しさの中に安定感を持たせる”ためのテクニックとして非常に有効です。
Driver → コンプレッサー(後段に配置):
- Driverで大胆に歪ませた音をコンプで締めることで、暴れすぎず、タイトで芯のあるサウンドになる。
- 特にキックやベースなど、低域が暴れやすい音に効果的。
アタックとサステインのバランスも整う。 - モジュレーションによって揺らいだ音を、コンプで一定のラウドネスに保つことで、聴きやすくなる。
コンプレッサー → Driver(前段に配置):
- あらかじめコンプで音量を整えてからDriverを通すことで、DISTOやCOLORの効果が安定的にかかる。
- 歪みが必要以上に偏らず、狙ったニュアンスを再現しやすい。
ボーカルやシンセに向いている設定。 - サウンドの下地を作ってからDriverでキャラクターを付けるイメージ。
サイドチェインコンプとの連携:
- Driverで歪ませたトラックも、他のトラック(例:キック)をトリガーにしてダッキング可能。
- 音同士がぶつからないように調整しつつ、Driverのインパクトを保てるため、ミックスの透明感が向上する。
EQとの組み合わせで得られる効果
Driverはフィルター機能を備えているものの、EQと併用することでより精密で狙い通りの音作りが可能になります。
特にディストーションをかけたあとは、倍音が増えて周波数が広がるため、EQで不要な帯域を整えることで音のバランスが取りやすくなります。
Driverで“荒くする”、EQで“整える”という役割分担を意識すると、よりクリアで使えるサウンドに仕上がります。
この結果として、Driverを大胆に使ってもミックス内でしっかりと機能する音を作ることができます。
Driver → EQ(後段に配置):
- Driverで歪ませて倍音を生成し、その後にEQで不要な帯域(特に高域のノイズや低域のブーミーさ)をカット。
- 高域が刺さりすぎる場合はシェルビングやピークEQで調整。
ディストーションの輪郭を残しつつ耳障りを防ぐ。 - 中域を軽く削ることで、音がこもらず抜けが良くなる。
EQ → Driver(前段に配置):
- 入力段階で音のバランスを整えておくことで、Driverの歪みやフィルターがより効果的に作用する。
- 低域を少し抑えておくと、DISTOによる過剰な飽和を防ぎ、スッキリした歪みに。
- 中域を持ち上げてからDriverに通すと、よりパンチの効いた音に変化する。
ピーク抑制やブーストの活用:
- Driverで強調された帯域をEQで微調整することで、他のトラックとの干渉を防ぎながら主張できる音作りができる。
- DRIVERのフィルターではできない細かい周波数のブーストやカットもEQなら対応可能。
Driverが向いている音楽ジャンルとクリエイター像
Driverは、幅広い音作りに対応する万能エフェクトですが、とくにその真価を発揮するのは“音を大胆に変化させたい”場面です。
フィルター、ディストーション、モジュレーションの3つを組み合わせることで、既存の音をまったく新しいキャラクターに変えることができるため、個性的で実験的なサウンドを求めるジャンルに最適です。
また、直感的な操作で複雑な動きが作れるため、音作りの経験が浅い方でも扱いやすい点も魅力です。
このことから、Driverは“個性を音に宿らせたいクリエイター”にぴったりのツールと言えます。
向いているジャンル:
- エレクトロニカ/IDM:
変則的なフィルター変化やモジュレーションが活きる。
複雑で不規則な動きが簡単に作れる。 - テクノ/ハードテクノ/インダストリアル:
DISTOで歪ませた金属的な質感や攻撃的なサウンドがマッチ。
キックやパーカッションに最適。 - Lo-Fi/アンビエント:
COLORで音の質感を柔らかくしたり、FILTERで空間的な奥行きを加えたりと繊細な演出が可能。 - ロック/エモ/インディ:
ボーカルやギターに軽い歪みとモジュレーションを加えることで、感情的で生々しい雰囲気が作れる。 - 実験音楽/サウンドアート:
SC入力やAM機能を使って、通常のエフェクトでは得られない非線形な音変化が楽しめる。
向いているクリエイター像:
- 定番の音に飽きた人:
プリセットから外れた音を自分の手で作りたいクリエイターに。 - DAW初心者~中級者:
操作がシンプルなので、直感で音作りを楽しめる。
深掘りすれば上級者も満足。 - 実験志向のトラックメイカー:
サウンドを“破壊→再構築”するような創造的手法を求めている人に最適。 - ライブ演奏で音の変化を重視する人:
モジュレーションの動きが自然で、演奏と連動するサウンド変化を演出できる。
推奨環境とDAW別の対応状況
Driverは、Windows・macOS両対応のプラグインで、主要なDAWソフトと高い互換性があります。
とはいえ、快適に動作させるには最低限のシステム要件を満たす必要があります。
また、DAWごとにプラグインの形式(VST、AU、AAXなど)が異なるため、Driverが対応しているか事前に確認しておくことが大切です。
このように、使用環境とDAWの仕様を理解することで、トラブルを未然に防げます。
- 対応OSと基本スペック:
Windows 10以降、またはmacOS 10.15以降に対応。
CPUはIntel Core i5以上推奨、RAMは最低4GB、できれば8GB以上が望ましい。 - 対応フォーマット:
VST2、VST3、AU、AAXに対応。
DAWがこれらの形式に対応していれば基本的に使用可能。 - Ableton Liveとの相性:
VST形式で安定動作。エンベロープやオートメーションとの連携もスムーズ。
Modulationの使い勝手が特に高い。 - Logic Proとの相性:
AU形式で問題なく動作。
フィルターとモジュレーションの操作が直感的に行えるため、エレクトロ系の音作りに適している。 - Studio One/FL Studio/Cubaseなど:
VST2/3に対応していれば全く問題なし。
DriverはDAWに依存しにくい設計なので、どの環境でも基本的な操作感は共通。
まとめ:Driverで音作りはもっと自由になる
今回の記事では、Native Instrumentsのエフェクトプラグイン「Driver」について、その機能と使い方を詳しく解説しました。
以下に要点を整理します。
- Driverはフィルター・ディストーション・モジュレーションを融合したサウンド加工ツール
- Envelope FollowerとAudio/Oscモードで“音の動き”を演出できる
- ボーカル・ドラム・キック・シンセなど幅広い音素材で活用可能
- プリセットを起点に、自分だけの音作りもできる柔軟な設計
- 他のエフェクト(リバーブ・EQ・コンプ)との組み合わせでさらに表現力が広がる
- 特にエレクトロニカ、テクノ、アンビエントなど“音色で世界観を作る”ジャンルに最適
このように、Driverは「単なる歪み系エフェクト」とは一線を画し、音を生きた表現に変える道具です。
「もっと音に変化をつけたい」「表情豊かなサウンドを作りたい」と思ったとき、Driverは確かな選択肢になるはずです。
ぜひ一度、プリセットを試しながら自分の音に“個性”を吹き込んでみてください。
価格:$49.00
>>>その他Native Instruments製品はコチラ
Plugin Boutiqueでの購入手順
特典のもらい方・ポイントの使い方
Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。
無料なので、必ずもらっておきましょう!
※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。


購入するプラグインをカートに入れます。
カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。
【ポイント利用方法】


Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。